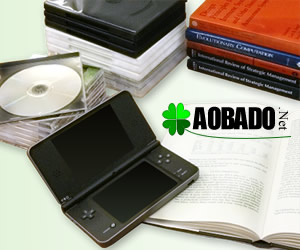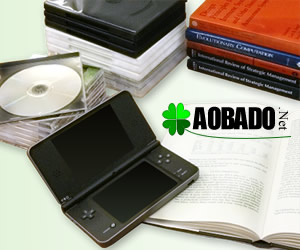
今年もいよいよ、あの「年末調整」の書類が人事部や総務部から配られる季節がやってきましたね。
私の周りでも、「ああ、またこの季節か」「面倒だなあ」という声が聞こえてきます。何を隠そう、私も20代、30代の頃はそうでした。「よく分からないけど、去年と同じ内容を書いて、ハンコを押して出しておけばいいや」と。
でも、40代になって資産運用や家計管理に真剣に向き合うようになって気づいたんです。その「なんとなく」の作業が、実は**年間数万円、人によっては十数万円の「損」**につながっている可能性がある、という事実に。
先日も、同世代の知人Aさん(45歳・会社員)と話していたら、「年末調整? 会社の経理がうまいことやってくれるんでしょ?」と本気で思っていたようです。
とんでもない!
年末調整は「会社が自動でやってくれる節税対策」ではありません。これは、**「税金を安くするための材料(情報)を、自分から会社に提出する作業」**なんです。
材料を出し忘れたら、当然、税金は安くなりません。つまり、本来払う必要のなかった税金を、余計に払い続けている(=損している)状態になってしまうのです。
この記事では、40代の私が、過去の自分や知人たちの失敗談も踏まえながら、「年末調整で見落としがちな節税ポイント」を徹底的に解説します。この記事を読み終える頃には、あなたはきっと「自分の書類、もう一回確認しなきゃ!」と焦り出すはずです。
第1章:【2025年・最重要】「定額減税」終了。だから今年は“本気”でやらないとマズい
本題に入る前に、今年(2025年分)の年末調整に特有の、非常に重要な話をさせてください。
結論から言うと、今年の年末調整は、昨年(2024年分)と比べて「還付金が減る」または「追徴額が増える」可能性が非常に高いです。
「え、なんで!?」と思いますよね。 答えはシンプルで、昨年(2024年分)に実施された「定額減税」が、今年(2025年分)はなくなるからです。
1-1. 昨年の「還付ラッシュ」を思い出してください
昨年、2024年は物価高対策として、1人あたり所得税3万円、住民税1万円の「定額減税」が実施されました。
6月以降、毎月の給与から引かれる税金が減っていた(月次減税)はずです。そして、昨年の年末調整(2024年分の精算)では、1年間の減税額(例:扶養家族含め3人なら 3万円×3人=9万円)を最終精算しました。 この影響で、「例年より還付金が多かった」「追徴額がほぼゼロになった」という人が多かったのではないでしょうか。
1-2. 2025年、私たちは「通常の税額」に戻る
しかし、この定額減税は2024年分のみの措置でした。 今年、2025年分の所得税を精算する今回の年末調整では、この「定額減税」はありません。
つまり、年収や家族構成、加入している保険が昨年とまったく同じでも、
- 単純に「定額減税」の3万円(+扶養家族分)だけ、税金の負担が(昨年に比べて)増える のです。
これは「増税」されたわけではなく、あくまで「通常の税額に戻る」だけです。 ですが、私たちの感覚としては「手取りが減る」「還付金が少ない」と、家計へのダメージを感じやすくなります。
だからこそ、どうでしょう。 今年の年末調整で、もし「生命保険料控除」や「扶養控除」といった、本来受けられるはずの控除を一つでも申告漏れしたら……そのダメージは、例年よりずっと大きく感じられるはずです。
「定額減税」というボーナスタイムが終わった今年だからこそ、私たちは“本気”で年末調整に向き合い、取りこぼしなく控除を申告して、自分の手取りを守る必要があるのです。
第2章:そもそも「年末調整」って何? なぜ「損」が生まれるのか?
では、改めて基本の確認です。なぜ年末にこんな面倒なことをするのでしょうか。
2-1. 年末調整とは「税金の精算作業」である
私たちは会社員として、毎月の給料から所得税が天引きされていますよね。これを「源泉徴収」といいます。
ただ、この毎月の天引き額、実は「仮払い」なんです。
なぜなら、その年の正確な所得税額は、1年間の総収入(1月~12月)が確定しないと計算できないから。さらに、「結婚して扶養家族が増えた」「生命保険に入った」といった個人の事情も、月々の給与計算には完全には反映されていません。
そこで、1年間の給与が確定する年末のタイミングで、「あなたの年収なら、本来払うべき税金は〇〇円でした」と正確な税額を計算し直します。
そして、それまで「仮払い」してきた合計額と、本来の税額を比べて、
- 仮払いが多かった人 → 差額が戻ってくる(還付)
- 仮払いが少なかった人 → 差額を追加で徴収される(追徴)
この一連の「精算作業」こそが、年末調整の正体です。 (そして前章の通り、今年は「定額減税」が適用されないため、還付が減るか、追徴になる可能性が高いのです)
2-2. なぜ「申告漏れ」が起きるのか?
ここで重要なのが、「本来払うべき税金」の計算方法です。税金は、年収(額面給与)そのものに課税されるわけではありません。
年収から、さまざまな「控除(こうじょ)」を差し引いた「課税所得」に対して、税金がかかります。
控除 =「この分は税金計算の対象から外しますよ」という割引枠
この控除が多ければ多いほど、課税所得は減り、結果として所得税も安くなります。
そして、ここが最大のポイントです。 会社が自動的に計算してくれる控除は、「給与所得控除(会社員の経費のようなもの)」や「基礎控除」、そして会社経由で天引きした「社会保険料(健康保険・厚生年金など)」だけです。
あなたが個人的に加入した保険、家族構成の変化、個人的に支払った国民年金などは、あなたが「申告書」に書いて会社に提出しない限り、会社は知り得ません。
この「自己申告」が漏れると、使えるはずの控除が適用されず、課税所得が不当に高いまま計算されます。結果、税金を払いすぎたまま精算が完了してしまうのです。これこそが「損」の正体です。
第3章:【最重要】申告漏れ多発!年末調整「書き忘れ」チェックリスト
あなたも失敗しないために、申告漏れが多い「控除」をリストアップしました。会社のデスクに届いた書類と、自宅に届いたハガキを見ながらチェックしてください。
3-1. 扶養控除の「申告漏れ」と「勘違い」
「家族構成なんて去年と変わってないよ」という人、本当にそうでしょうか? 状況が変わった人だけでなく、「勘違い」による申告漏れが多発しています。
- 知人Bさんの失敗談(大学生の扶養) 私の知人Bさん(48歳)は、大学生のお子さんに仕送りをしています。そのお子さん、昨年まではコンビニで年間150万円ほどアルバイトをしていたため、「扶養」から外れていました(※年収103万円を超えると税法上の扶養から外れます)。 しかし、今年は就職活動に専念するため、アルバイトを辞め、年収は50万円ほどになったそうです。Bさんは、年末調整の書類(扶養控除等申告書)を、昨年と同じ「扶養親族なし」のまま提出してしまいました。 **これが大失敗。**大学生(特定扶養親族)を扶養に入れると、「63万円」もの所得控除が受けられます。Bさんの所得税率が20%だったと仮定すると、住民税(一律10%)と合わせて、約18.9万円も税金が安くなる可能性があったのです。
- 【要注意】高校生の扶養と「児童手当」の勘違い これが2025年、非常に多い「勘違い」です。 2024年12月から児童手当が改正され、所得制限が撤廃、支給対象も高校生まで延長されました。 これを聞いて、「じゃあ、高校生の子どもを扶養に入れたら、児童手当がもらえなくなる(あるいは、児童手当をもらってるから扶養控除は使えない)んだな」と勘違いして、扶養控除(38万円)の申告をためらう人がいます。 それは明確な間違いです! 「児童手当」と「税法上の扶養控除」は全く別の制度です。児童手当が高校生まで支給されるようになっても、**年収103万円以下の高校生(16歳~18歳)は、変わらず「扶養控除」の対象(控除額38万円)**になります。 もし税率20%の人なら、住民税と合わせて年間約11.4万円の節税になります。絶対に申告漏れしないでください。
3-2. 生命保険料控除:3枚のハガキ、全部出してますか?
これは定番ですが、漏れが多いものです。10月頃に保険会社から「控除証明書」というハガキや封書が届いているはずです。
チェックポイントは、「一般生命保険」「介護医療保険」「個人年金保険」の3つの区分があること。この控除だけで、所得税は最大12万円、住民税は最大7万円、課税所得を減らせます。ハガキ1枚が数千円から数万円の価値があると思って、家中を探してみてください。
3-3. 地震保険料控除:火災保険とセットになっていませんか?
「うちは地震保険は入ってないから」とスルーする人も多いですが、ちょっと待ってください。
地震保険は、多くの場合「火災保険」とセット(付帯)になっています。火災保険の証券や、送られてきた控除証明書をもう一度よく見てください。「地震保険料」という記載はありませんか?これも最大で所得税5万円、住民税2.5万円の控除になります。
3-4. 社会保険料控除:自分の給与天引き「以外」がキモ
年末調整の書類には「社会保険料控除」という欄があります。 「これは給与天引きされている健康保険や厚生年金のことだろ? 会社が知ってるはずだ」 そう思って空欄で出す人がいますが、半分正解で、半分不正解です。
会社が把握しているのは、あくまで「あなたの給料から天引きした分」だけ。 もしあなたが、「生計を一にする家族」の社会保険料を支払った場合、その全額が「あなたの」控除対象になります。
これは節税効果として非常に強力です。なぜなら、生命保険料控除のような「上限額」がなく、支払った額が「全額」控除されるからです。
【具体例】
- ケース1:大学生の子どもの「国民年金」を支払った 20歳になると、学生でも国民年金(2025年度なら月額17,510円、年間約21万円)の支払い義務が生じます。もし、お子さんの国民年金保険料を、親であるあなたが支払った場合、その約21万円全額があなたの所得から控除されます。
- ケース2:年の途中で退職した配偶者の「国民健康保険料」を支払った 配偶者が会社を辞めてフリーランスになったり、次の就職先が決まるまでの間、国民健康保険に加入することがあります。その保険料(世帯主であるあなたの口座から引き落とされている場合など)も、あなたが支払ったものとして控除できます。
これらは、会社は絶対に把握できません。あなたが「払いましたよ」と申告書に金額を書き、証明書(国民年金の場合は控除証明書が送られてきます)を添付して初めて適用されます。
3-5. 【超重要】iDeCo(イデコ)の申告漏れ
老後資金と節税対策のために「iDeCo(個人型確定拠出年金)」に加入している40代は多いでしょう。 これも掛け金が「全額」所得控除になる、最強の節税策です。
しかし、会社員がiDeCoに加入している場合、年末調整での「自己申告」が必須です。(※企業型DCのマッチング拠出で、給与天引きの場合は不要なこともあります)
10月~11月頃に、国民年金基金連合会から**「小規模企業共済等掛金払込証明書」**というハガキが届いているはずです。 このハガキに書かれた「年間払込額」を、年末調整の「保険料控除申告書」の右下にある「小規模企業共済等掛金控除」の欄に記入し、**ハガキそのものを添付(提出)**しなければなりません。
これを忘れると、どうなるか。 仮に月2万円(年24万円)をiDeCoで積み立てていた場合、税率20%の人なら、住民税と合わせて年間約7.2万円もの節税メリットが、丸ごと吹き飛びます。 ハガキ一枚、書き忘れ一つで7万円を失うのです。これほど恐ろしい申告漏れはありません。
3-6. 寄附金控除(ふるさと納税):ワンストップ特例、使いましたか?
数年前から「ふるさと納税」をしている人は多いでしょう。 ここで状況が二つに分かれます。
- A:ワンストップ特例を申請した人 寄付した自治体が「5つ以内」で、各自治体に「ワンストップ特例申請書」を(通常、寄付の翌年1月10日までに)提出した人。 この場合、翌年の「住民税」から自動的に控除(減額)されるため、年末調整での手続きは一切不要です。
- B:確定申告が必要な人 「6つ以上」の自治体に寄付した人、申請書を出し忘れた人、もともと医療費控除などで「確定申告」をする予定の人は、年末調整では処理できません。年明けにご自身で「確定申告」をする必要があります。
第4章:年末調整では対応不可!でも「確定申告」すれば取り戻せる控除
年末調整の期限(だいたい11月~12月初旬)に間に合わなくても、諦める必要はありません。年が明けてから「確定申告」をすれば、払いすぎた税金は(5年間さかのぼって)取り戻せます。
特に以下の4つは、会社員でも確定申告が必要になる代表例です。
4-1. 医療費控除:家族全員分で「10万円」超えていませんか?
これは非常に強力な控除ですが、年末調整では扱えません。 年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が、家族全員分(生計を一にしていればOK)の合計で「10万円」(※所得200万円未満の人は所得の5%)を超えた場合、その超えた分が控除の対象になります。
対象範囲はあなたが思っているよりずっと広く、病院代、薬代のほか、通院のための交通費(公共交通機関)、子どもの歯科矯正(美容目的は不可)、レーシック費用、出産費用(一時金を引いた額)なども含まれます。
40代ともなると、自分や配偶者の持病の治療費、子どもの歯列矯正、親の介護費用などがかさむ時期です。領収書は1年間集めておく習慣をつけましょう。
4-2. 1年目の住宅ローン控除(2025年入居の注意点)
マイホームを買った方、おめでとうございます。住宅ローン控除(減税)は非常に大きな節税策です。
ただし、**購入した「1年目」だけは、年末調整では処理できません。**必ずご自身で確定申告をする必要があります。面倒なのは最初の1年だけです。 2年目以降は、税務署から送られてくる「控除申告書」と、金融機関の「残高証明書」を会社に提出すれば、年末調整で処理してもらえます。
【2025年・注意点】 2024年・2025年に入居した場合、制度が少し変わっています。「子育て世帯(18歳以下の子あり)」や「若者夫婦世帯(夫婦どちらかが39歳以下)」以外は、控除対象となる借入限度額が縮小されています。今年(2025年)家を買って初めて確定申告をする人は、ご自身の物件がどの基準(省エネ基準など)を満たしており、いくらまで控除対象になるのか、契約書などで確認しておきましょう。
4-3. 雑損控除:災害や盗難に遭った場合
これはあまり起きてほしくないことですが、台風、地震、洪水などの自然災害で住宅や家財に損害を受けた場合や、盗難、シロアリ駆除などで予期せぬ出費があった場合、「雑損控除」を受けられる可能性があります。これも年末調整ではなく、確定申告が必要です。
4-4. 副業所得が20万円を超える場合
もし会社員として働きながら、副業(フリーランスのライター、週末のアルバイトなど)をしている場合、その所得(収入から経費を引いた額)が年間20万円を超える場合は、原則として確定申告が必要です。
第5章:今からでも間に合う?年末調整「駆け込み」節税アクション
「この記事を読むのが遅すぎた!もう11月だ!」 大丈夫です。年内(12月31日まで)に行えば節税につながるアクションがいくつかあります。
5-1. ふるさと納税(12月31日まで)
これは鉄板ですね。12月31日までに寄付(決済)を完了させれば、その年の寄付として扱われます。まだ寄付枠が残っている人は、駆け込みで利用しましょう。
5-2. iDeCo(個人型確定拠出年金)
これは「最強の節税策」です。 「じゃあ今年はもうダメか」 いえ、今から手続きを始めれば、「来年」の年末調整で丸1年分の控除が受けられます。老後資金の準備と、将来の大きな節税のために、今すぐ資料請求だけでも始めておくことを強くお勧めします。
5-3. 個人年金保険・生命保険の加入(12月中の契約・払い込み)
もし保険の見直しを考えているなら。年内に契約し、1回目の保険料を払い込めば、その年の控除対象として認められるケースが多いです(※保険会社や商品によりますので、必ず確認してください)。
まとめ:年末調整は「年に一度の権利」。書類提出は「作業」ではなく「投資」
ここまで読んでいただき、ありがとうございます。 年末調整の書類仕事は、確かに面倒です。「会社に言われたからやる」という受け身の「作業」だと捉えると、苦痛でしかありません。
しかし、視点を変えてみてください。 年末調整は、「国が認めた節税の権利」を行使する、年に一度のチャンスです。
特に、定額減税がなくなった今年(2025年分)は、この「権利行使」が例年以上に重要です。 この書類に、あなたが支払った保険料や家族の情報を正しく書き込むことは、未来の自分への「投資」と同じです。数千円、数万円が戻ってくる(あるいは余計に引かれない)のですから。
「児童手当と扶養控除」の勘違い、「iDeCoの申告漏れ」……これら一つで数万円の「損」が確定します。
「よくわからない」を放置し続けると、あなたは「通常の税額」に戻った現実+「控除の申告漏れ」のダブルパンチで、来年以降も損をし続けることになります。
まずは、今年の年末調整の書類をもう一度引っ張り出してきてください。 「申告漏れ」はありませんか? 「あのハガキ、どこいったっけ?」と探してみてください。
もし会社の提出期限に間に合わなくても、まだチャンスはあります。年明けに「確定申告」をすれば、払いすぎた税金は(多くの場合5年間)取り戻せますから、諦めないでください。
賢く制度を利用して、自分の資産をしっかり守っていきましょう。
【免責事項】
- 本記事は、年末調整や税制に関する一般的な情報提供を目的として作成されています。執筆時点(2025年11月)の情報に基づいています。
- 税法や制度は将来的に改正される可能性があります。2025年分の年末調整(令和7年分)に関する情報は、必ず国税庁の最新情報をご確認ください。
- 記事の内容は、特定の個人の状況に対する税務アドバイスを構成するものではありません。具体的な税務処理や申告については、必ず税理士や税務署などの専門家にご相談ください。
- 本記事の情報に基づいて被ったいかなる損害についても、筆者およびnoteは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- iDeCoや保険商品への加入は、ご自身の判断と責任において行ってください。